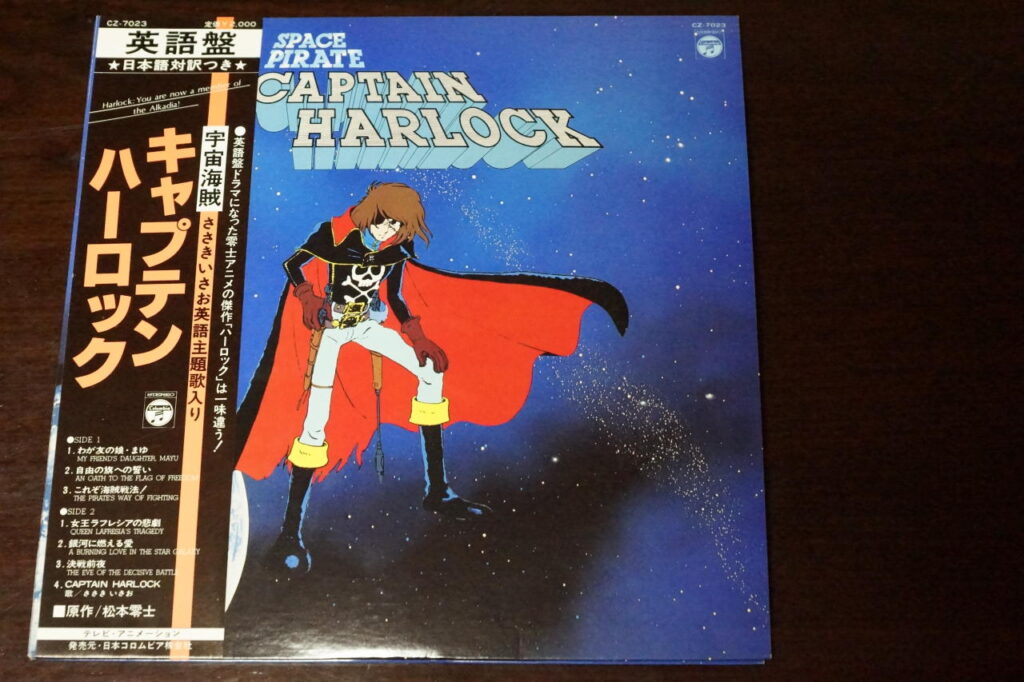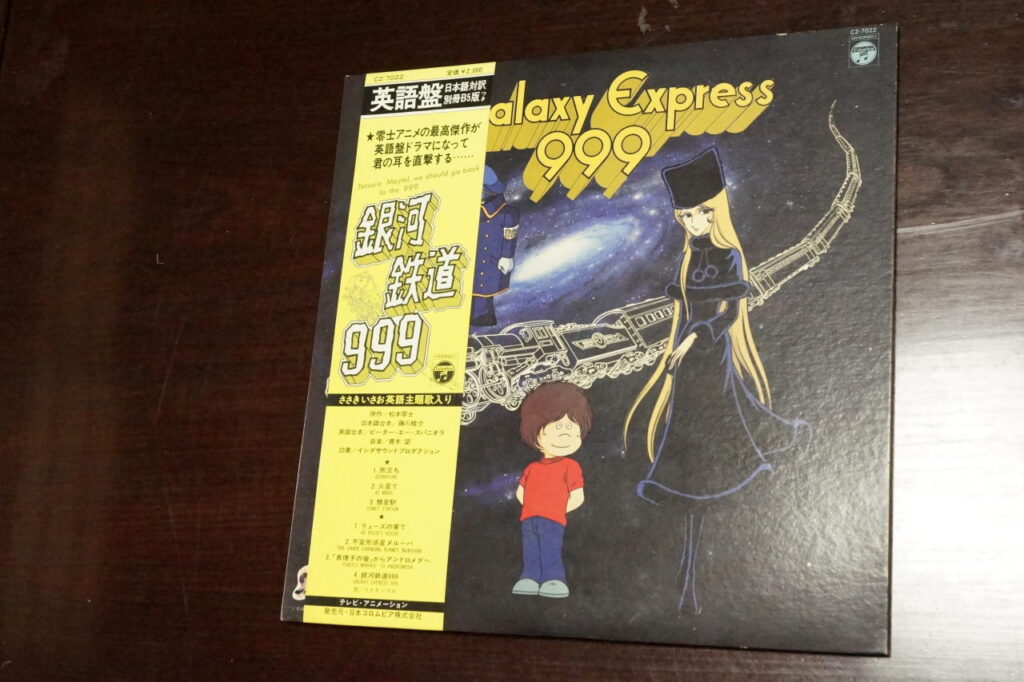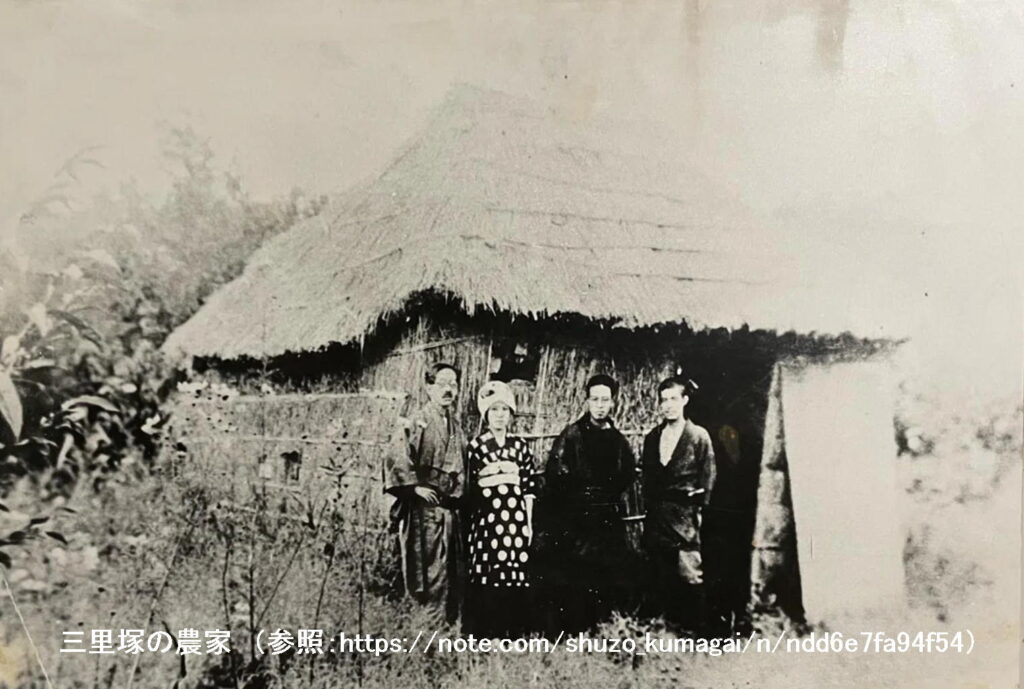これまで世界に最も影響力を与えて来たのはG7(Group Seven)であったが、次第にその影響力を失い、今では単なるお仲間国の集会となりつつある。今後世界で最も影響力を持ちそうなのはD3である。Dとは何かと言うとDictatorship=独裁国の事である。具体的にはロシア、中国、米国である。
ロシアと中国が独裁国であることは衆人が認めるところであろうが、米国が独裁国と言うには疑問を差し挟まれる方もおられると思うが、トランプは大統領に就任してから独裁者の道を邁進している。憲法を無視して自分のやりたい政策を進めるところは独裁者そのものである。
今回米国はロシアの原案に基づくウクライナ‐ロシアの和平案を纏めようとしている。独裁者を目指すトランプとしては独裁者の先輩であるプーチンによりシンパシーを感じるのであろう。金正恩に友情を感じたり、習近平と接近を図るのも彼らが独裁者の先輩であるからだ。
そして、このD3の連携が完成した時、世界は恐ろしい事態に直面する。何しろこのD3の中には世界第1位と第2位の経済大国が含まれるからだ。軍事力においても世界1位から3位までを独占し、経済力と軍事力でそれ以外の国は対抗しようが無い。世界経済を自由に操ったり、ウクライナ侵略のように他国へ侵攻しようとやりたい放題になる。
まだ米国での独裁体制が完成した訳では無い。しかし、トランプは残りの大統領の任期中に自分の独裁体制を強固にするような改革を推し進めるだろう。あるいは自分が大統領を退任しても次の大統領を陰で操る院政を敷くかもしれない。
第一次大戦後、世界最良の憲法はワイマール憲法だといわれた。しかし、独裁者ヒトラーはそのワイマール憲法から生まれている。民主主義国家から極めて民主的に独裁者が生まれる事はある。